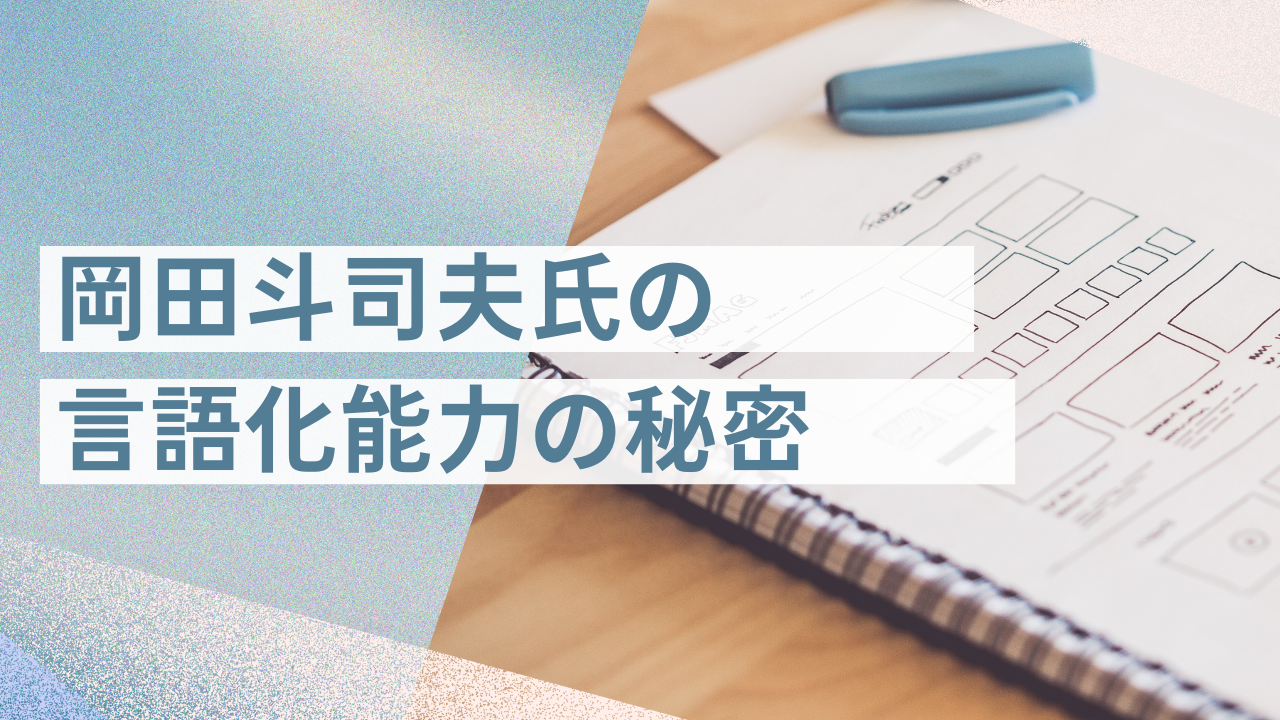岡田斗司夫氏は、社会評論家、作家、そしてアニメ制作会社ガイナックスの元代表プロデューサーとして知られ、その多岐にわたる活動の中で一貫して卓越したコミュニケーション能力を発揮しています。
この言語化能力が注目され、多くの人々がその秘訣を知りたいと願うのは、氏が「評価経済社会」のような新しい概念を提唱したり、「ぼくたちの洗脳社会」といった著作で社会の深層に切り込んだりする際に見せる、鋭い洞察力とそれを分かりやすく伝える能力にあります。
多くの人々が自らの考えを明確に表現することや、複雑な情報を理解することに困難を感じる現代において、岡田氏のコミュニケーションは効果的なモデルを提供していると言えるでしょう。
岡田氏の言語化は、単なるスピーキングスキルに留まらず、知性と個性が融合した一種のパフォーマンスと捉えることができます。自らを「オタキング」と称し、膨大な読書量に裏打ちされた広範な知識ベースを持つことは、その発言の深みと多様性を支えています。
さらに、岡田氏自身が「サイコパス」的側面を公言し、それを感情に左右されず物事をプラスかマイナスかで判断できる性質と結びつけて語っている点は、時に過度な感情移入を排した、客観的で論理的な、それゆえに明晰な言語表現に繋がっている可能性が考えられます。
この期待は、岡田氏自身が「ユニバーサル・トーク」や「戦闘思考力」といったコミュニケーション手法を著作で詳述し、具体的な思考訓練法を提唱していることからも裏付けられます。